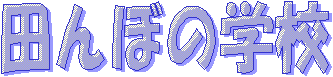
=稲作り体験学習=
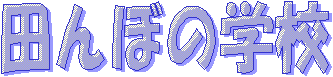
1 はじめに小学校の社会科において、第5学年では「日本の産業と私たちのくらし」について学習します。4年生までの地域社会の追求を大切にしながら、日本の産業に従事する人々のくらしを高めようと努力し苦労している姿について考えていきたいと思っています。そして、情報もただ収集するだけでなく、自分なりにまとめて発信する力をつけていきたいと考えています。 その産業の中の農業に携わる人々のくらしについて学習する中で、米作りを体験させたいと考えました。「米」という子どもたちにとっても身近なものについて、体験し考えていくことは、より学習が深まることだと思います。 そこで、本年度は、田んぼでの米作りをぜひ体験させたいと考え、保護者のお力を借りることにしました。あわせて、稲の成長について毎日観察できるようにJAグループが主催している「バケツ稲作り」を利用し、学校でも継続観察・世話をしていくことにしました。 さらに、総合的な学習の時間でも米の品種や産地・流通について調べる活動や,米の食べ比べや旭町の米づくりを調査したりする活動を通して,「米作り」についてこだわっていきたいと考え計画を立てています。 2 本学習における目標●おいしいお米を作るためのひみつを進んで調べようとする。 ●友達と協力して,調べたことをまとめて発表する。 ●旭町の稲作や畑作について疑問や関心を持ち,進んで調べる活動を通して地域の土地の様子や特徴に気づく。 ●旭町の稲作や畑作に携わっている人々に目を向け,それぞれの人々の思いを知る。 5月28日(火)
社会科の時間に,日本の農業について学習した。世界の中でも上位にランキングされるほどの生産量を誇る稲作について学習した。旭町にもたくさんの田んぼがあり米づくりが行われている。「ぼくたちも米を作ろう。」という声もあった。【田植え】 保護者の計らいで田んぼを借りることができた。米づくりのプロに教わりながら,田植えを体験することにした。 |
|
 |
旭町北に住む結石さんが苗を用意してくださった。5〜6本ずつに分けたものを子どもたちに手渡し,もみまきから苗作りの様子についてお話してくださった。 植えた苗は「キヌヒカリ」だそうだ。 |
 |
結石さんの奥さんと町内の愛育委員さん方3名も来てくださった。 綱を引っ張ってくださったり,植え方を教えてくださった。 代かきをした田んぼに入るのは初めてという子どもたちがほとんどで,足を踏み入れるやいなや「うわ〜」と歓声とも悲鳴とも言い難い声があちこちから聞こえた。 |
 |
ぎこちない足取りと手つきで田植えが始まった。 苗はあっちに向いたりこっちに向いたり。 でも,そろそろ終わりに近づいた頃にはそこそこの手つきでスピードも出てきて上手になってきた。 |
|
≪児童の記録より≫(別紙参照) ☆稲の根っこを見ると、もみがらがついていた。どうしてもみから植えないんだろう。 ☆稲が田んぼに立つように植えた。田植えがこんなに大変だとは思わなかったです。田植えが終わるととても気持ちよかったです。 5月30日(木) 【バケツ稲田植え】 |
|
 |
先日の田植え体験を生かして,今度はバケツ稲栽培に挑戦。 土は栄養たっぷりの田んぼの土を保護者の方より提供していただいた。 まず,土を手で細かく砕いてバケツに入れた。水を入れると土は少なくなってしまった。また土をたしながらバケツの7分目くらいまで入れた。なんと,手で代かきを始める子が続出。 |
 |
分けていただいた稲を6〜7本丁寧に分けて,バケツに植えた。 種もみを発芽させた「アキタコマチ」と「コシヒカリ」については,プラスティック船に直まきにして生長を見ることにした。これまた,船の中で服をどろどろにしながら代かきをした。 「無農薬・有機栽培にしよう。」とこだわりを持ち始めた子もいた。 |
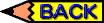 TOPへ
TOPへ