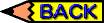点訳タイプライター
|
西暦1825年に、フランスの盲目少年ルイ・ブライユによって現在世界各国で使われている六点式点字と、その配列表が創案された。しかし、その点字がフランスの公式文字として採用されたのは、1854年であった。 日本では、1890年(明治23年)にルイ・ブライユの創案したした点字を東京盲学校教師石川倉次が、日本の文字に翻訳した。 点字は、縦3点、横2点の六つの組み合わせからなる世界で最も合理的な表音文字である。六つの点にはそれぞれ番号がついており、右上の点を1の点、右中の点を2の点、右下の点を3の点、左上の点を4の点、左中の点を5の点、左下の点を6の点という。 点字は、横書きで右から左へと書く。読む場合は、原則として紙をひっくり返して凸面を左から右へ読む。しかし、よく目の見える人の中には凹面(点字を打った方)を上にして右から左へ読む人もいるが、これはこれで差し支はない。 点字を書く器具を点字器という。点字器は、点字板と定規と点筆とからなり、定規は連結した方を左にして点字板にはめる。定規の上金にあるわくをマスという。点字板の紙あさえのマスは、頁をつけるためのものである。 紙は点字板にあてて片側のあまった部分を折り、折った方を右側で上に向けて、点字板の紙おさえにはめる。裏面に書くときは、紙おさえの上の方の針であいた穴を下の方の針にさして固定する。 点筆は、上の平らな部分を人差し指の手のひらがわにあて、親指、人差し指、中指の3本で握り、紙に対して垂直に書く。 点訳とは、漢字かなまじり文をかな文字(点字がな)だけに置きかえることである。そこで、活字の文章を正しく読み、うつすことが点訳の生命となる。かならず辞書をひき、読み方をたしかめて書くことを心がけていただきたい。 点訳では、かな文字だけを使うので、言葉の区切りをはっきりさせるために、わかち書きをする。言葉を自立語と付属語(助詞や助動詞)にわけ、自立語の前はマスあけをし、付属語は自立語に続けて書く。また熟語はその意味Ⅰ(言葉の成熟度やアクセントも関係してくる)によってわかち書きをする。 点字に対して、正眼者の使う文字を墨字という。印刷された文字、タイプされた文字、手書きの文字のいずれもいう。 |