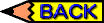|
 |
| 受精卵と5ヶ月(500g)、7ヶ月(1000g)、10ヶ月(3000g)の胎児模型 |
講師 東森 二三子先生
(母と子のステーション・NPO法人「ミントハウス」)
内容
助産婦である東森先生は、これまでたくさんの赤ちゃんをとりあげた経験や相談事例をふまえながら、貴重なお話をしてくださいました。
心に残っている例を紹介します。
 生まれるときは、お母さんも大変だけど、生まれてくる赤ちゃんのほうがもっと大変。2000m以上の山のような酸素があまりないところを通って出て来るようなもの。
生まれるときは、お母さんも大変だけど、生まれてくる赤ちゃんのほうがもっと大変。2000m以上の山のような酸素があまりないところを通って出て来るようなもの。 最近では、生まれたての赤ちゃんをへその緒がついたまま、お母さんのお腹に乗せるという産院が増えている。すると、赤ちゃんは這い上って、お乳を見つけて吸うそうだ。
最近では、生まれたての赤ちゃんをへその緒がついたまま、お母さんのお腹に乗せるという産院が増えている。すると、赤ちゃんは這い上って、お乳を見つけて吸うそうだ。 5kgで生まれてきた赤ちゃん、660gと740gで生まれた双子の赤ちゃん、990gで生まれてきた赤ちゃんなどいろいろな赤ちゃんがいる。ふつうに10ヶ月3000gほどで生まれてきた赤ちゃんよりも、ずっと苦しんで生まれ、一生懸命生きてきたのに、ぐず・のろまなどと言われて、いじめを受け、学校に行けなくなってしまった例もある。でも、みんなだいじな子ども。のろま・ぐずなどと言わないでほしい。
5kgで生まれてきた赤ちゃん、660gと740gで生まれた双子の赤ちゃん、990gで生まれてきた赤ちゃんなどいろいろな赤ちゃんがいる。ふつうに10ヶ月3000gほどで生まれてきた赤ちゃんよりも、ずっと苦しんで生まれ、一生懸命生きてきたのに、ぐず・のろまなどと言われて、いじめを受け、学校に行けなくなってしまった例もある。でも、みんなだいじな子ども。のろま・ぐずなどと言わないでほしい。 いじめを苦に、包丁で自殺しようとしたのを、母親が気づいて止めてくれた。その時、誤って手に包丁が当りたくさん血が出た。二人で、思いっきり泣いたが、母が、「せっかく一生懸命産んだ命だから、大切にして・・・・」と言って私をなでてくれた。
いじめを苦に、包丁で自殺しようとしたのを、母親が気づいて止めてくれた。その時、誤って手に包丁が当りたくさん血が出た。二人で、思いっきり泣いたが、母が、「せっかく一生懸命産んだ命だから、大切にして・・・・」と言って私をなでてくれた。命がけで産んでくれた両親→産んだだけで100点

命がけで生まれてきた子ども→生まれてきただけて100点
 母が祖母のお腹にいたとき、その母の体のなかには、もう母の子(自分)のもと(原始卵胞)があった。ずっと命はつながっている。
母が祖母のお腹にいたとき、その母の体のなかには、もう母の子(自分)のもと(原始卵胞)があった。ずっと命はつながっている。 体の変化・心の変化について
体の変化・心の変化についてさらに、子どもたちと会話をしながら、わかりやすく第二次性徴に関わる内容についても教えてくださいました。
*赤ちゃんと自分たちとの違いは?
へその緒がついていない。大きさ、重さ、髪の毛などが違う。
歩ける。食べれる。話ができる。

*おうちの人と違うところは?
(男):ひげ、声、おちんちん、毛、胸毛
(女):お乳、生理、体つき
など
早い遅いはあるが、大人にするホルモンが出てだんだん変わってくる。
生理:子宮にいつ子どもが入ってきてもいいように、ベッドができる。1カ月くらいして、いらないベッドが外に出るのが、生理。
精通:だんだんおちんちんが大きくなり、精子が作られるようになる。いっぱいになると外に出る。夜寝ていてパンツに出ることがあるが、隠さなくてよい。精子3〜4CCに3〜4億個。赤ちゃんができる確立は8億分の1。
 小学生からの手紙を紹介
小学生からの手紙を紹介学校が始まって、うれしいやら楽しいやら悲しいやら。生理になってしまい、保健室で寝るハプニング。血の量が不規則なことも心配。ナプキンは、ハンカチでくるんだほうがいいの?
アドバイス:生理は、命を生み出す前の大事な変化、お母さんのようになる準備なので安心してほしい。
《授業後の学級懇談で》
 東森先生より
東森先生より
●県北でも東京と変わらない状況で、中高生でも、中絶したりしているという現実がある。情報は、全国どこでも同じように入ってくる。出会い系・コンビニ・雑誌など。良い悪いではなく、流されてしまう傾向が強い。軽い気持で付き合い、すぐに最後までいってしまう・・・。
●祖父母との同居家庭が多いと思うが、家族が多いと、かえって母と子や父と子のふれあいが少なくなりやすい。家の中の力関係は、小さい子でもよくわかっている。祖母が強いと子どもは、祖母に気を使って、祖母の近くに行くようになってしまうことが多い。その方が家の中がうまくいくとわかっているから・・・・。でも、本心は、母が一番と思っている。だから、母が本心をベールに包んで、「おばあちゃんがええんじゃろ。」と突き放したりしていると、「母はわたしを産みたくて産んだんだろうか?」と愛情不足を感じ、その代償をすぐに異性に求めがち。
だからこそ、仕事が忙しくても、ふれあいを持ってほしい。中学生までは、男子は母と女子は父と、一緒にお風呂に入ってしっかりふれあってほしい。スキンシップは、つらいことに出会った時の力になる。また、親子でいっしょに生理日を記録する習慣をつけてほしい。(カレンダーなどに付け合って・・・)娘の妊娠を母親が気づかない例も多い。そういう習慣がついていれば、大変なことになる前に、気づくことができる。
さらに、虐待を受けた子どもや不妊治療を受けて生まれたきた子どもの事例を紹介してくださいました。
大事に産んで、大事に育てている、大事な存在である。
生きているだけで100点
という気持を親子だからこそ、しっかりと伝え合ってほしい。それができていれば、だいじょうぶだということをお話しくださいました。
 保護者の感想
保護者の感想●わかりやすくとてもよかった。わが子が産まれてきた時のことを思い出した。そのころは、産んだ後は離す時代だった。命の大切さをあらためて考えさせられ、心に残るよい話だった。祖父母との同居だが、親としての心がまえは?
アドバイス:しっかりふれ合う。一人ひとりの子どもとふれ合っていく。小さいうちは、いろいろなモーションをかけてくるけれど、12歳ぐらいになると、あまり表さなくなり、話をしなくなる。そして、17歳で爆発する。子どもは、親に認めてもらいたいもの。夫婦は、パートナーに認めてもらいたいものである。
●「生まれてきて100点」「小学生のうちにスキンシップ」ということを聞いて、うちの子はかなり甘える方なので、これでいいのかと思っていたが、安心した。
●子どもが生理の話をしてくるので、どう話していいのか困っていたが、わかってよかった。
●祖父母との同居であるせいか、長男があまり自分の方には来なかったのに、中学生になって話をよくするようになった。そんななかで、妹ばかりかわいがるということを言われた。
●上の子は、「もうお父さんとは、風呂に入らない。」と言うようになり、少し寂しい気がしている。
●子どもの面倒は、祖母がよくみてくれているが、甘やかしすぎではないので、たすかっている。しかし、学校であったことなどは、祖母には話しにくい様子。話す時間をどうつくっていったらよいのか?
アドバイス: べったりでなくても、話ができる時にすればよい。「どっちが好き?」と子どもに聞かれたら、内緒で「あなたが好き」と答えるとよい。「どっちも好き」では満足しない。ちょっとした気づかいを自然体でするとよい。
●性教育参観日というと、今まで、体の違いに関する内容が多く、見ている方も少しはずかしかった。今日は、抵抗なく話が聞けた。子どもは男の子なので様子もよくわからず話がしにくかったが、今日の授業がよいきっかけになり、よかった。
●親の方も産んだ時の感動を思い出した。生まれた時の話をしっかりしてやらなくてはと思った。仕事の都合や祖父母と同居ということで、母乳をやっている時だけが親子の時間だった。とても葛藤があったが、スキンシップをしっかりするようにとアドバイスを受けた。今でも、ちょっとした時にふれ合いを持つように心がけている。子どもの方も、肩をもんでくれたりなど気遣ってくれる。
●このごろ、生理の話を姉たちとよくするようになった。
●本当にきてよかった。やはり、祖父母と同居しているが、子どもたちがそれぞれに「なあ、おかあさん。」と何回もいうことがある。
今日の話を聞いて安心した。
●もう、はずかしがってあまり話をしないが、姉とはお風呂に入って話をしている様子。また、下の子のめんどうをよくみてくれているので、「助かるわ」などとは言うようにしている。
アドバイス:子どもは、親を喜ばせようとしていい子にしていることが多い。下が甘えるとうらやましいが、自分はできない。「いい子でなくていいんだよ。」ということを伝える必要がある。たまには、「いっしょにお風呂に入ろう。」と声をかけてやってほしい。たぶん、本当はそれをのぞんでいるのでは・・・?
●母親は、弟の世話で忙しいので、上の二人は張り合い、時にはすねたりすることもある。とくに、まん中の子は、「お母ちゃんは、○○ちゃんのほうが好きなんだな」と言うこともある。
アドバイス:まん中の子に気持を補ってやるとよい。お風呂で無理に話さなくてもいい。中学生であっても、心は甘えたいもの。子どもはやがて確実に離れて行く。その時には、追わないこと。1年に10cmずつ離れていくとよい。
●子どもに「どっちが好き?」と聞かれた。ないしょで、「あなたが好き」と答えたが、ないしょにできずに、その後がたいへんだった。
お風呂も寝る時も互いに張り合って、母親の取り合いをしている。このまま、しっかりスキンシップをしていきたい。
●生まれた時のことを、車の中で話したことがある。兄弟それぞれ様子が違っているので、自分がどれなのかはわかっていないかもしれない。自分が母親にどう思われているか、あまり気にしていないのではないかと思う。子どもの方からは親に甘えにいきにくくなっているようで、こちらから近づくと離れるが、夕食の準備のときなどは、てつだいながら、よく話をしてくれる。
●機会を見つけて、その都度話をするようにしている。まだまだ親のそばにいたい様子。
●上の子は、「もうお父さんとは、風呂に入らない。」と言うようになり、少し寂しい気がしている。
●子どもの面倒は、祖母がよくみてくれているが、甘やかしすぎではないので、たすかっている。しかし、学校であったことなどは、祖母には話しにくい様子。話す時間をどうつくっていったらよいのか?
アドバイス: べったりでなくても、話ができる時にすればよい。「どっちが好き?」と子どもに聞かれたら、内緒で「あなたが好き」と答えるとよい。「どっちも好き」では満足しない。ちょっとした気づかいを自然体でするとよい。
●性教育参観日というと、今まで、体の違いに関する内容が多く、見ている方も少しはずかしかった。今日は、抵抗なく話が聞けた。子どもは男の子なので様子もよくわからず話がしにくかったが、今日の授業がよいきっかけになり、よかった。
●親の方も産んだ時の感動を思い出した。生まれた時の話をしっかりしてやらなくてはと思った。仕事の都合や祖父母と同居ということで、母乳をやっている時だけが親子の時間だった。とても葛藤があったが、スキンシップをしっかりするようにとアドバイスを受けた。今でも、ちょっとした時にふれ合いを持つように心がけている。子どもの方も、肩をもんでくれたりなど気遣ってくれる。
●このごろ、生理の話を姉たちとよくするようになった。
●本当にきてよかった。やはり、祖父母と同居しているが、子どもたちがそれぞれに「なあ、おかあさん。」と何回もいうことがある。
今日の話を聞いて安心した。
●もう、はずかしがってあまり話をしないが、姉とはお風呂に入って話をしている様子。また、下の子のめんどうをよくみてくれているので、「助かるわ」などとは言うようにしている。
アドバイス:子どもは、親を喜ばせようとしていい子にしていることが多い。下が甘えるとうらやましいが、自分はできない。「いい子でなくていいんだよ。」ということを伝える必要がある。たまには、「いっしょにお風呂に入ろう。」と声をかけてやってほしい。たぶん、本当はそれをのぞんでいるのでは・・・?
●母親は、弟の世話で忙しいので、上の二人は張り合い、時にはすねたりすることもある。とくに、まん中の子は、「お母ちゃんは、○○ちゃんのほうが好きなんだな」と言うこともある。
アドバイス:まん中の子に気持を補ってやるとよい。お風呂で無理に話さなくてもいい。中学生であっても、心は甘えたいもの。子どもはやがて確実に離れて行く。その時には、追わないこと。1年に10cmずつ離れていくとよい。
●子どもに「どっちが好き?」と聞かれた。ないしょで、「あなたが好き」と答えたが、ないしょにできずに、その後がたいへんだった。
お風呂も寝る時も互いに張り合って、母親の取り合いをしている。このまま、しっかりスキンシップをしていきたい。
●生まれた時のことを、車の中で話したことがある。兄弟それぞれ様子が違っているので、自分がどれなのかはわかっていないかもしれない。自分が母親にどう思われているか、あまり気にしていないのではないかと思う。子どもの方からは親に甘えにいきにくくなっているようで、こちらから近づくと離れるが、夕食の準備のときなどは、てつだいながら、よく話をしてくれる。
●機会を見つけて、その都度話をするようにしている。まだまだ親のそばにいたい様子。
 学校・町保健センターより
学校・町保健センターより●今回のように性教育という枠だけでなく、子育てについて話ができたら・・・と思う。
●一人の親として話を聞いた。大事なことを思い出させてもらって、元気が出る気がした。子どもたちの心にもしみわたったと思う。一人でできることは限られている。困った時、助けてほしい時、支えになってくれるものがあると生きる大きな力になると思う。東森先生には、これをきっかけに、そのような力になっていただきたい。
●町保健センターとしても、子どもたちが健やかに育ってほしいということから、東森先生を紹介させてもらった。やはり、一母親として話を聞かせてもらった。節目節目の気持を思い出させてもらうのはとてもいい。心の成長に目を向けるきっかけにしたい。今は、大切なものを見失いがちな、子育てがしにくい世の中になっている。少しでもサポートできたらと考えているので、何でも話しに来てほしい。