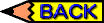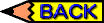学習活動 | 指導上の留意点 | 資料等 |
1本時のねらいを知る
|
- 自分が家族に似ているところから、父親、母親の両方から生まれたということを知らせ、生命の誕生への動機づけとする。
| |
2赤ちゃんが生まれる
しくみについて知る
|
- 母親の体の中には「赤ちゃんのタマゴ」である「らんし」があることを知らせる。(形・大きさ)
- 父親の体には「赤ちゃんのモト」である「せいし」があることを知らせる。(形・大きさ・作られている場所)
- 「らんし」と「せいし」いっしょになって「新しい命」が生まれることを知らせ、命は父母、祖父母・・・・とずっと続いていることに気づかせる。
|
お母さんの絵
ペープサート(らんし)(せいし)
針
お父さんの絵 |
| 3赤ちゃんがおなかの中で育つ様子について知る |
- 針の先ほどの小さな生命が約9か月かかって子宮の中で大事に育てられている様子をカレンダーと胎児模型を使って視覚的にとらえさせる。
- 子宮、たいばん、へそのお、よう水についても知らせる。
|
お母さんの絵(子宮の中)
胎児模型
月カレンダー |
4赤ちゃんが生まれる様子について知る
|
- せまい赤ちゃんの通り道を通って、やっと出てきたことを知らせる。
|
|
| 5学習のまとめをする |
- 小さな小さな生命が、約9か月間おなかの中で大事に育てられ、やっと生まれてきたのが今の自分であることに気づかせ、命を大切にしようとする心を育てる。
|
|
事前指導 |
- 生活科の学習と関連させ、自分が誕生したときの身長、体重やそのときの様子などを家族に聞いたり、母子手帳、アルバムなどを見たりしながら誕生に関心をもたせる。
|
|
事後指導 | |
|